| |
|
|
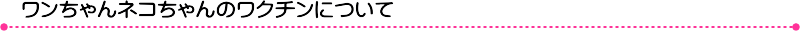 |
| |
  |
| |
 |
愛すべきあなたのワンちゃん・ネコちゃんの生命・健康を脅かす感染症はたくさんあります。 |
| |
その中でワクチンで予防できるものについて、簡単にご説明します。 |
| |
通常、狂犬病を除くワクチンは仔犬・仔猫の時期に2~3回、あとは毎年1回の接種がのぞましい |
| |
です。ただし、混合ワクチンの接種は飼い主に任されている任意のワクチンです。 |
| |
|
 |
ワクチン接種はワンちゃん・ネコちゃんの体調の良い日を選び、平日の午前中にお越しいただく |
| |
ことをおすすめしています。 |
|
注射後免疫が出来るまでの2~3週間は、他の動物との接触を避けるようにしましょう。 |
|
注射後、激しい運動やシャンプーをひかえるなど注意して、体調を崩さないようにしましょう。 |
| |
|
 |
| |
|
 |
狂犬病/原因 (ウイルス) |
|
|
|
罹患した動物に噛まれることにより感染し、死亡率はほぼ100%の病気です。 |
|
『狂犬病』という文字だけを見ると犬だけにかかる病気のように思えますが、哺乳類すべて |
|
感染する狂犬病ウイルスを病原体とした人獣共通感染症です。 |
|
人畜共通伝染病の中で最も恐ろしく悲惨なものといわれています。 |
|
昭和32年以後、日本での発生はありませんが多くの国々ではまだまだたくさん発生していて |
|
いろいろな動物が輸入されているため油断はできません。 |
|
犬を飼う場合には飼い犬を狂犬病から守ると同時に、社会責務として「狂犬病予防法」に |
|
基づく飼い犬の登録と狂犬病予防注射の接種が義務づけられています。 |
| |
|
 |
ジステンバー/原因 (ウイルス) |
|
|
|
全身を侵され発熱、嘔吐・下痢などの消化器症状、咳・膿状の鼻汁などの呼吸器症状、 |
|
てんかん発作・痙攣などの神経症状を起こし死亡率は高く、治ってもいろいろな後遺症に |
|
悩ませられることが多いです。 |
| |
|
 |
伝染性肝炎/原因 (ウイルス) |
| |
|
|
アデノウィルス1型による感染症で肝炎を主とし嘔吐や下痢、食欲不振、角膜の混濁など |
|
が起こります。 |
| |
|
 |
犬パラインフルエンザ/原因 (ウイルス) |
| |
|
|
犬パラインフルエンザウィルスによる感染症で、肺炎や扁桃炎などの呼吸器病を起こります。 |
| |
|
 |
パルボウイルス感染症/原因 (ウイルス) |
| |
|
|
激しい嘔吐、血様の下痢、脱水、白血球減少症を起こす腸炎型と仔犬が突然死する |
|
心筋型があり伝染性が非常に強く、死亡率も高い恐ろしい病気です。 |
| |
|
|
 |
| |
|
|
 |
猫ウィルス性鼻気管炎/原因 (ウイルス) |
| |
|
|
猫のヘルペスウイルスが原因で起こる猫の風邪の一つです。 |
|
風邪の様々な症状(咳、くしゃみ、目やに、発熱、食欲不振など)が出て重症になりやすく |
|
下痢などの胃腸症状も出ることも多く食欲がなくなり食事が食べられなくなるため、急激な |
|
衰弱や脱水症状が起こり死亡することもあります。 |
|
生後6ヶ月未満の子猫などは、病気の進行が早く、死亡する危険性も高いです。 |
|
また、症状が表れなくても、猫の体の抵抗力が衰えた時に発病する事もあります。 |
| |
|
 |
猫カリシウィルス感染症/原因 (ウイルス) |
| |
|
|
はじめはクシャミ、鼻水、発熱などの「カゼ」ですが症状が進むと舌や口周辺に潰瘍ができる |
|
ことがありときには急性肺炎を起こし死亡することもあります。 |
| |
|
 |
猫汎白血球減少症/原因 (ウイルス) |
| |
|
|
猫パルボウィルスによる感染症で、白血球が極端に減少して食欲が無くなり、高熱、嘔吐、 |
|
下痢が続き激しい脱水症状となる。 |
|
体力の無い仔猫などはたった1日で死ぬこともある恐ろしい病気です。 |
| |
|
 |
猫白血病ウィルス感染症/原因 (ウイルス) |
| |
|
|
白血病やリンパ腫、免疫力を弱めるため、他のいろいろな病気にかかりやすくなります。 |
|
感染した猫は80%が3年以内に死亡するといわれています。 |
|
|
|
 |
|
|
 |
ワンちゃんには熱中症にかかる危険が高いといえます。 |
| 体の表面には汗腺がほとんどなく肉球にのみ汗腺があります。体温の放散は、呼吸器による |
|
空気の出し入れにより行っています。つまり、暑さに対しては大変弱いため注意が必要になります。 |
|
|
 |
ネコちゃんはとてもデリケートな生き物で、日によって食欲があったり、なかったりします。 |
| 元気そうなのに何日間か食べなかったり、吐き気があったり、あまり排便せず、気になって |
|
動物病院を訪れ、触診、聴診、血液検査、尿や便検査などにより健康状態をチェックしても何の |
|
“異常”も発見できないことがあります。 |
|
そんなとき疑ってみる「病気」のひとつが「毛球症」で胃や腸など消化器官内に毛玉ができる |
|
症状です。レントゲン撮影には毛の固まりは映りません。 |
|
大きくなれば、開腹手術で毛玉を取り出すことになります。 |
|
軽い初期の段階では毛球除去剤を猫の口元に塗り、ペロペロなめさせる方法があります。 |
|
|